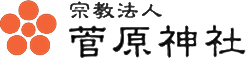杜のことづて

2012.11.09
私達の自然
(5) 無常と挽歌
自然は依然として生あるものに、陽光に満ちた恵みを与えると共に、蔭りと不毛そして死をもたらします。私達の国では、古代には前者が、中世には後者が比較的注視されたと言えるかもしれません。万葉集では自然にこと寄せた歌がとても多く、大いなる不動の自然への信頼があるように感じます。それに対して中世の方丈記では、人の世も自然にも不動のものは無く(人が自然の一部であれば人の変化は自然の変化でもありますので) 、盛者は衰え不動の自然も荒廃するなど、全てのものは流転してゆくという見方、つまり無常が全体を覆うように強調されます。(山林での厭世はやはり自然への信頼に繋がるようですが。) しかしそれは傾向としてであり、万葉集にも方丈記の無常ほど強調的ではないものの、世の無常を嘆く歌もあります。そして古代よりその死に応ずるように挽歌が詠われてきました。
挽歌は万葉集以来、和歌や詩歌の一分野として定着しています。亡くなった人を悼み偲ぶ歌で、死という、自然の最も不可思議な一側面に向き合う歌でもあります。有名な例を挙げれば、万葉集に、柿本人麻呂による亡き妻(最愛の通い妻なのでしょう)への泣血哀働歌群があります。そして近代では宮沢賢治の「春と修羅」に、病死した最愛の妹への無声慟哭群、オホーツク挽歌群があります。(賢治は自分を、妹の「信仰を一つにするたったひとりのみちづれ」(無声慟哭)と記しています。)
人麻呂の歌は長歌が主、賢治のものは長い心象スケッチなのでここに掲げるのは控えます。また人麻呂はしばらく通っていなかった妻の死を、便りを運ぶ者から聞かされるのであり、賢治は妹の死に最後まで立ち会っているという、死に接する状況に大きな違いがあります。さらに千三百年ほどの隔たり、全く異なった環境、境遇、古語と今の言葉という表現上異なった言葉で詠まれたにもかかわらず、愛する者への両者の挽歌は悲痛と苦悩、虚しさと嘆き、諦め(きれぬ思い)等が混ざり合いつつ率直に表明されていて、最終的には何か共通した他に替えられない感慨、抒情の原形が浮かび上がります。
「第一群が全体に主観的な傾向を示してたかぶる心情を吐露するのに対し、第二群が総じて客観的傾向を示して諦めの心情を流露する」(伊藤博 萬葉集釈注一)という人麻呂についての言葉は、そのまま賢治の無声慟哭群とオホーツク挽歌群についても当てはまるように思えます。(但し「永訣の朝」と「松の針」は未だ妹は死に瀕している状況で詠われており、挽歌と言えるかどうか判りませんが) 勿論その対比は時の流れによってもたらされるものですが、最愛の人の死に対して人が持ちうる最も親密な心情も、一般的に強から弱への経時的変化があるのでしょう。しかしこの変化もあくまで傾向としてです。
人麻呂第一群の長歌では、亡き妻が本当に死んだとは受け入れられず、どうしてよいかわからず、妻がよく出かけた賑わう市に一人出てみるものの、妻の似姿もなく音も聞こえず、それでも名を呼び袖を振って、長歌は終わります。また第二群でも、慰めに妻の姿を見たと人が言う「羽がひの山」に「岩根さくみて なずみ来し」(注)と詠み、決して諦観しているわけではないことがわかります。最愛の者が永遠に不在となる状況では、ある程度時が流れても諦観などできないのは当然かもしれません。賢治はオホーツク挽歌全体の終わりに「・・/わたくしのかなしみにいぢけた感情は/ どうしてもどこかにかくされたとし子をおもふ」(噴火湾(ノクターン))と記しました。
(注)岩を押し分けて苦労してやって来た
医師は生と死の分かれ目まで、人の生理の終わりまで立ち会いますが、詩人は、生と死の分かれ目に立ち会いつつ、その分かれ目を言葉で乗り越えようとし、死の側に越境してまで言葉を紡ぎます。亡き妹の赴いた行方を、「・・/ とし子はみんなが死ぬとなづける/ そのやりかたを通って行き/ それからさきどこへ行ったかわからない/ それはおれたちの空間の方向ではかられない/ 感ぜられない方向を感じようとするときは/ たれだってみんなぐるぐるする/ ・・」(青森挽歌)のように、「はかられない」世界を「ぐるぐる」しながら追憶と現実と幻想の間を迷いつつ行き来しつつ記していきます。もちろん越境してもそこは死の世界、決して言い当てることのできないことは承知の上で、それでも言葉を紡ぐほかないという現実があります。「・・/けれどもとし子の死んだことならば/ いまわたくしがそれを夢でないと考えて/ あたらしくぎくっとしなければならないほどの/ あんまりひどいげんじつなのだ/ ・・」(青森挽歌)
人は自分の死や死後について経験できないわけですが、他者の死を外側から経験してはいます。その他者が自分にとって最も近しい人の場合、自らの死の経験に近いものとなるのかもしれません。二人の挽歌は親密な者の死に心から潜り込むことで、死を他者の死とともに自らも経験してゆく営みではないでしょうか。人麻呂の挽歌が、たとえ妻の死後暫く経ってからの作品化であっても、初めの長歌が昨日のことと思わせる臨場感を湛えていることを見ればなおのこと、人麻呂の妻の死への潜伏度は強かったのだと感じます。また賢治は、妹の死に沈潜しつつ、「・・/わたくしの感じないちがった空間に/ いままでここにあった現象がうつる/ それはあんまりさびしいことだ/ (そのさびしいものを死といふのだ)/ ・・」(噴火湾(ノクターン))等と記しています。
最愛の者を亡くすことは、自らも「ふすま道(注)を 引手の山に 妹を置きて 山道を行けば生けりともなし」(泣血哀働歌第二群)の状況になるのでしょう。「ふすま道よ、その引手の山にあの子を置いて、寂しい山道をたどると、とても自分が生きているとは思えない。」(伊藤博氏による現代訳) この状況を無常と言うことも出来るでしょうが、人麻呂も賢治もこの挽歌では、諦観~無常に抗して言葉を紡いでいるように感じます。無常の中に入ってしまえば、それ以上言葉を費やす必然もなくなるでしょう。言葉によって測りがたい死に形を与え、死を顕在化させ、親しき者の行方が無常にのみ込まれぬような意味(心の中の共同の墓標でしょうか)を求めることが、この挽歌を詠む大きな契機になっているのではと思えます。二人の挽歌は(死という)無常に向かい合い、言葉の力によって死に形と意味を与えて、無常を乗り越えようとする営みでもあるように思えます。
(注)「ふすま」は寝るとき上にかける寝具の意ですが、「ふすま道(じ)」は「引手の山」にかかる枕詞とされます。